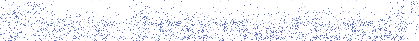知的財産権(知財)法からみた、電子商取引(EC) -- 知的所有権:特許:ビジネスモデル特許:電子決済システムの問題 |  |
1. はじめに | ||
まず、電子商取引が現実的に有効に機能する際に、国際的な標準が存在すべきなのか、また、標準化が行われた際に、どの様な問題が起こりえるのか、先ず日本の知的財産法とりわけ工業所有権に関する条約を考察した後、問題を探ってみる。また、広義の産業政策のなかでの、知的財産権の占める割合は大きく、特に、米国における知的財産権に関する政策や解釈の変化が、国際的なルールづくりにどのように影響を与えてきたのか、まとめて検討したい。(アンチパテント→プロパテントの確立への推移)
1992年11月アメリカのシティーバンクが、日本特許庁に対して「電子通貨システム」と呼ばれる発明にたいして特許請求を行った。電子マネーの発行から支払い、入金、銀行間決済といった電子金融の一連のシステムを特許範囲として請求している。一方、これに特許認可が下った場合、業界全体をカバーする独占的な金融ネットワークが形成され、もって、ネットワーク使用料や、加入認可権の乱用など、不公正かつ独占的なシステムになることは想像に難くない。しかし、米シティーの特許を日本で認めないことになると、世界的な標準から取り残され、強いては日本金融界の孤立化を招く恐れも十分に考えられ、日本の産業政策上、好ましくない。シティーバンクが、独自に開発した電子マネーシステムに対する特許を世界20カ国に対し出願したことは、世界中の金融機関を震撼させた。事実、日本の主たる都市銀行(第一勧銀、富士銀行、さくらなど)は、「新規性がない」などとしてこの出願に対する異議を申し立てた。それほどまでに銀行がこだわるのはなぜか、一つは、このシステムが世界中で特許を取ることになると(シティーバンクは20ヶ国で特許申請をしている)、世界での金融システムの事実上の標準ができあがり、もって銀行が今まで有していた「決済」と「与信」機能がシティーバンクの手中に握られてしまうこと、また、このシステムが世界的な標準として用いられた場合、莫大な額の使用権を米シティーバンクに対して払わなくてはならなくなるからである。シティーバンクは、1992年11月に特許庁に出願、1995年同月に出願公告された。しかし、一方で、NTTが「電子商取引(エレクトロニックコマース)で受け取った電子マネーをそのまま即座に別の電子取り引きにも使える」という、内容の特許をシティーバンクに先駆けて持っているという話もある。(1996年3月13日付日経産業新聞「ネット・ビジネス死角アリ」)
では、もし日本に於いて認められ、この特許権に対する侵害(勝手に利用すること)が行われた場合、いかなる措置がとられるのであろうか。特許権侵害に対しては、損害賠償のほか、侵害行為の排除や差止め請求が認められるのが通常である。つまり、邦銀としては、もしこのシステムが世界的な標準になるとするならば、という仮定をおくとしたとき、世界的な流れにのらなくては国際的な流れであるEDI(電子データ交換)に乗り遅れることになるため、莫大な金額の使用料を払わなくてはならないのである。そこで、以下に、日本の工業所有権制度について述べ、若干特許要件についての判例を紹介した後、パリ条約がらみから考察したいと思う。
#余談であるが(本当は非常に重要)、すでに日本でもこの特許がとられてしまった、という話もある。だが、私見では、このシステムは「特許」と呼ぶにふさわしいものなのか、素人の目から見て、いささか疑問が残る。(※注1)
2. 知的所有権(知的財産権)とは | ||
2.1 知的所有権と独占禁止法
知的所有権(一部、この翻訳を嫌い、知的財産権という。(中山など)
:※注2)は、intellectual propertyの訳語とされ、「知的創作物の模倣行為あるいは営業条の模倣行為に対する権利」(田村)であるとされている。具体的には、技術に関する発明を保護する特許法、デザインを保護する意匠法、技術に関する考察を保護する実用新案法、文化的な創造物を保護する著作権法、営業上の表示を保護する商標法などがあり、特に著作権法を除くものには、工業所有権法という別の名前がつけられている。また、国際的な取り決めとして、工業所有権保護に関するパリ条約や、PCT(特許協力条約)があり、更に、ガットウルグアイラウンドにおいて成立したTRIPs協定などもその範疇に含まれる(更に、ハーモ条約や、著作権に関わるヘーグ条約などがある)。さて、工業所有権との関係においてよく問題になるのが、独占禁止法である。これら2つは、産業の発達に寄与する、という共通の目的があるものの、その達成する為の方向性が異なるわけだが、歴史をひもといてみると、その時代時代の産業政策により、どちらかの理念が衰退したり、どちらかが強大な力をもったりしたものである。独占禁止法は、独占的なシェアを誇る企業の対等により、産業の健全な育成がはばかられることを防止することを趣旨とする法律であるが、アメリカでは、ニューディール政策時代(アンチパテント)には独占禁止法が強化され、特許法などが有名無実化した事もある。1952年の特許法改正の流れをうけ、両法は調和をはかってきたが、1980年代にいたって、事情は一変し、米国はプロパテント時代の到来とともに、独占禁止法政策の後退を余儀なくされた(CAFCの設立と判例法の統一にもとづく:1982年)。独占禁止法23条によると、「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法または商標法による権利の行使と認められる行為についてはこれを適用しない」が、いったん権利が認められたからといって独禁法の網にかけることが完全にできなくなるわけではなく、この問題については様々な議論がある。一言コメントさせていただくと、その中で特許法はその目的からして、「発明の保護および利用を図る事により発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する事(特許法1条)」が重要であり、もしも発明者に独占的な利用の権利を与えないと、発明をしようとする人がいなくなってしまう、ということから考えると、あくまで比較衡量がはかられなければならない、という事である。
2.2 特許法の日米比較
日本の特許法の歴史は古く(アメリカの方がもっと古いが)、改正も時代の要請にあわせて数多くなされて来た。現在では、特許を取れる発明の要件として、以下のような点が挙げられる。つまり、特許出願前に日本国内において 1 公然知られた発明 、2 公然実施された発明 、3 あるいは外国において頒布された刊行物に記載された発明、をのぞいたものであることである。また、発明の保護対象として、「物の発明」「方法の発明」「物を生産する方法の発明」が挙げられ、以前はソフトウェアは発明にはあたらないものとされていた(この点については後述)。今回のシティーバンクの出願している特許は、「物の発明」でも「物を生産する方法の発明」でもなく、「方法の発明」である(しかも、あくまで「ビジネスの方法」である:この点についても、後述する)。従って、発明の「実施」にあたる行為は、あくまで「その方法を使用する行為」のみとなる。次に、日本とアメリカの特許法の違いを簡単に触れるが、日本や欧州の特許法は「先願主義」を採用しており(特許法39条)、一方アメリカの特許法は「先発明主義」を採用している、つまり、「最も早く発明していた人」が発明者であるとの認定がなされる、ということである(しかも、アメリカは自国民には「先発明主義」・外国人には「先出願主義」を採用しているのだから、たまったものではない)。また、(これは1996年1月に改正法が施行されたそうだが)アメリカの特許制度では、「出願の公開」がなされなかった。次に、「特許期間」が日本・欧州では「出願後」20年であるのに対し、アメリカでは「成立後」17年となっている事である。(よって、アメリカでは、意図的に発明者が特許成立を引き伸ばす事ができる・・・サブマリン特許)
平成6年特許法改正附則(1)
○附則第8条:特許付与後の異議申立て制度導入に伴う経過措置について規定したもので、原則として、迅速な権利付与のニーズにマッチさせるべく、改正法の施行前に出願した特許についてもこの異議申立てが認められる事になっている。しかし、既に出願公告(この制度は新特許法で廃止)がなされ、仮権利が生じているものに関しては、排除される。ということは、シティーバンクの特許は、既に仮権利がなされていたのであるから、(仮権利発生は去年の11月)これは以前の特許法の「事前異議申立て」制度が使われ、事後救済はできないことになってしまう。
出願公開制度(2)
○出願公開とは、特許出願日から1年6ヶ月を経過した後に出願内容を公開する制度で、これは、出願から特許になるまで長い時間を要し(特に日本では、10年もの年月がかかるものもある)、第3者が同じような発明の研究開発を進めてしまう可能性があるからである。しかし、この制度は特許法の平成6年改正でなくなった。
2.3 パリ条約
パリ条約とは、工業所有権の国際保護に関する同盟条約であり(1条)、本来一国の産業政策上の問題といえるものに、各国法制の違いを斟酌しつつ、できる限り調整法としての枠組みで可能な限りの工業所有権の国際保護という目的を達成するため、・同盟条約である・開放条約である・無制限条約である などの特色を有している。さらに、保護内容の特色(パリ条約の3大特色)として、1 内国民待遇の原則(2条) 2 優先権制度(4条) 3 各国特許独立の原則(4条の2)がある。「内国民待遇の原則」とは、パリ条約同盟国が工業所有権の保護に関し、他の同盟国民に、内国民と差別することなく平等の待遇を与えることをいう(2・3条)。「優先権制度」とは、同盟国が他の同盟国に出願する際の言語的、地理的不平等を制度的に克服し、もって内国民待遇の実効性を手続き面から担保するために採用された制度で、同盟国民による正規の同盟第一国出願に基づき同一対象について同盟第二国出願をするさいに、第一国出願時に出願したならば得られたであろう利益を第二国出願に与える条約上の特別の利益を「優先権」という。(4条)「特許独立の原則」とは、同盟国の国民が書く同盟国で出願した特許は他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとする原則(4条の2)とされ、ここが特許製品の並行輸入の並行輸入の議論で大いに問題となるところである。日本の特許法は、パリ条約に基づいて規定されているものが多いが、自己執行的規定のばあい、憲法98条を介して、特許法26条により「直接適用」される。(パリ条約 2条・4条・4条の2・5条の3など)
3. アメリカの知的所有権(知的財産権)に対する保護の強化 | ||
1950年に連邦最高裁で下された「グレーバータンク事件」で、原告のリンデ・エア・プロダクツ社が所有するカルシウムとマグネシウムの珪酸塩を含むフラックスに関する特許紛争で、被告の製品はカルシウムと「マンガン」であった。しかし、連邦最高裁は被告らの製品と原告の製品が「均等物」すなわち同じ物だと認定して、特許侵害を認めた。しかし、独禁法が強化された50年代から60年代にかけて、均等論による特許の範囲の拡大は認められなかった。(「特許ライセンスの日米比較」29P)例えば、1970年代、ゼロックスが、特許侵害を理由にアメリカの他の複写機会社を訴えた事件では、逆にゼロックスの方が独禁法違反で基本特許3件を無料公開、残りを有料公開させるという事態になってしまった。(「強い基本特許有効な取り方/係争の争点」333P)インスタントカメラの用のカラーフィルムの供給をコダックに依頼していたポラロイドが、コダック側の謀反と同社の特許侵害を理由とする訴訟に勝利した事件は、1976年に連邦地方裁判所に提訴されたが、この頃はアンチパテントからプロパテントへの移行時であり、もしこれが独禁法が幅を利かせていた時代に提訴されていたら、逆に独禁法違反でポラロイドが負けていたかもしれない。さらに、原告ハネウェルと被告ミノルタの特許訴訟では、「均等論」がまさしく問題となり、特許の範囲から言うと文言上は何ら抵触しなくても、「同一の方法で、同一の機能を果たし、同一の結果を得る」のであれば両者は均等とみなされる結果、被告側が「真似した」とみなされたのである。「特許の有効性」が極端に高くなったという大きな違い・あるいは特許侵害に対する損害賠償額の巨大化も見逃せない。
この歴史的な変革の裏には、アメリカの国家の威信をかけた、「知的所有権の強化に伴うアメリカの再生」、という姿勢がある。1930年から40年代は、ニューディール政策に伴い、「独占」が忌み嫌われ、その結果として、特許制度は大きく衰退した。1950年から60年代は、1952年の改正特許法の施行(非自明性の導入など:103条)に伴い、特許制度と独禁法の調和が図られたが、依然として対立していた(上記のクレーヴァータンク事件の少々後で、ゼロックス事件の頃にあたる)。1980年代は、2人の大統領(カーター&レーガン)の政策により、パテントの強化がなされるようになった。(知的所有権に対するアメリカの対外圧力が強くなったのもこの頃から)特に、1982年のCAFC(連邦巡回区控訴裁判所:13番目で、ワシントンDCにおかれている。特許審査を専門としている。)の設立により判例法が統一され、またセカンダリーコンシダレーションと特許の有効性の強化や、均等論の強化と禁反言の制限、がなされた。アメリカの特許法では、必ずしもアメリカ特許が有効なものではなく、ただ単に有効であると推定されるだけである(米国特許法282条)から、特許侵害紛争では、侵害の有無に加えて、その特許の有効性自体が争われる。有効性の推定にかんして、CAFCは従来の判例を変更し、特許庁において検討されなかった先行特許が侵害訴訟で提出されても、有効性の推定は否定されないとしている。
セカンダリーコンシダレーションとは、技術の専門家ではない裁判官の為に、商業的成功の有無などを考慮して「非自明性」を推定する制度で、その中には、「同時期の発明」をもってクレームの自明性を推定する、というのも含まれる。(3)
4. 特許制度の判例 | ||
4.1 発明とは?
日本で言う「発明」は、自然法則を利用した科学的思想の創作のうち高度なものをさし、数字や記号を組み合わせた暗号作成は特許法にいう発明とはいい難いとの判例がある。(しかし、古い)また、以前はソフトウェア自体に特許性は認められていなかったが、最近では、新しい審査基準の導入により、フロッピーディスクやCD-ROMに書き込んだソフトに特許権が認められ、これを模倣したソフトを書き込んだディスクの販売・製造・輸入は、特許侵害として差し止められることが可能となった。これは、以前はソフト自体の保護は著作権任せになっており、ハードウェアに組み込まれて一体とならなければ特許権が認められないとされていたことからすると、かなりの進歩であるが、ソフト開発業者の中には、登録料のコストがかかったり、新規開発の場合の確認の費用を考えて、「逆に開発コストの上昇につながる」との懸念があるのも事実である。(日経 4/3) 個人的にも、ソフトウェアの保護を著作権にばかり求めるのではなく、特許性を認め、もってソフト業界の活性化を図るべきであると考える(ハードウェアは、ソフトがなければただの箱)。勿論、この特許性の期間をもっと考慮すべきであるが。(1982年の中山論争:ソフトウェア立法の提言)
4.2 特許成立要件
※一般的な考え方
特許成立要件(in Japan)
1 特許法上の保護対象は「発明」
2 「発明」のうち、一定の要件を満たしたもの
注)一定の要件=産業上の利用可能性、新規性、進歩性
特許成立要件(in America)
1 特許法の保護対象(法定の主題)は、「方法、機械、製品、合成物、
またはこれらの改良」である (米国特許法101条)
2 上の保護対象に含まれるものの中で、有用性、新規性、非自明性があるもの
とすると、金融商品やサービスに関する特許権が成立する際に問題となるのは、
2よりも1の方(つまり、特許適格性の要件)であろう。
実際、米国のPTO (Patent and trademark office)の審査便覧(manual of patent examining procedure)で、特許法の保護対象(法定の主題)に含まれないものとして、印刷物、天然物、科学原理、とならんで、「ビジネスの方法」をあげている。これが、今まで日本の金融機関が、金融商品などにあまり力を入れていなかった(勿論、今までの護送船団方式にもよるだろうが)原因の一端となっているものと解することができ、今後、日本の金融機関がどういう対応をしていくのか、非常に興味があるところである。
日本での「発明」の要件として、1単なる精神活動、2 純然たる学問上の法則、3人為的な取り決め等、一定の者に独占を認めるよりは誰もが利用できた方が産業の発展にしするものは、除外されるとされている。一方、米国での「法定の主題」(発明の要件)のなかで、1 自然法則(law of nature)、2 自然現象(natural phenomena)、3 抽象的なアイデア(abstract idea)は、特許の対象にならないとされている。しかし、アメリカでは、特許の対象が拡大解釈され、今では、コンピューターの応用による生産理念や数学的発明、バイオテクノロジーによる高等動物への遺伝子組換などにも特許が認められるようになってきている。いかに、その例を少々挙げてみる。
例1:カーマーカーの数学特許
本来、世界のどの国に於いても数学的発明には「特許」を与えない方針であった。(日本の特許法における「発明」は、「自然法則を利用した」ものでなければならず、 その点において、数学はそれ自体では発明とはならない)しかし、数学自体が産業に利用されるようになる、例えば、産業的なシミュレーションや数値計算などで威力を発揮するようになると、産業界での重要性は高まる。カーマーカーの特許はこうした流れの中、ATT(アメリカン・テレホン・アンド・テレグラム)により出願され、アメリカでは1988年5月10日/90年4月3日、EP(ヨーロッパ特許)では、90年10月10日/89年10月11日にそれぞれ認められた。(日本では、未審査・あるいは拒絶審査)
カーマーカー特許は、線形計画法をもちいて長距離電話網での回線割当てや電話網管理などで、システムコストを最小限とするものである。線形計画法などの数学的解法は本来は特許の対象ではないが、この解法を純数学的に用いることをクレームとしたのではなく、産業的に応用することのみをクレームとした。これにより、「数学的な知識自体はクレームされておらず、学問的知識自体を特許により独占するという不都合が回避されうる」
例2:生産理念の特許性とATTのCIM特許
CIMとはコンピューターをつかった統合生産であり、コンピューター管理による省力化工場の決め手となるものである。CIMは、新たな生産の理念であり、これを理念のままで特許を認めることが可能なのか。実施例として、「電気回路の設計から製造までをコンピューターの管理により行う」ことがあげられよう。そして、これは実際アメリカで特許をとった(日本では不出願)。これも、ビジネスの手法と考えられるが、コンピューターを使っている点で、保護される可能性が高かったといえる。
このように、アメリカとしては、国家の産業政策上重要と思われるものに対してどんどん特許性を認め、産業を活性化させようとする動きを見せている。(勿論、この背景にはCAFCの設立とそれに伴う判例法の統一、更に、セカンダリーコンシダレーションと特許の有効性の強化があげられる)特に、コンピューターが産業界に深く根をおろすにつれ、特許の範囲は拡張されなければならないのはいうまでもなく、今後更なる議論が出てくる事であろう。(更に、コンピューターソフトウェアに対して50年間の保護期間をもたせるのかいなか、というのも興味深い問題である。)
4.3 金融システムに関する特許紛争(ビジネスの手法の特許性)
裁判例(金融システムに関する特許紛争:アメリカ)
<Hotel Security Checking事件>
事案:レストランにおいてウェイターが売上金を横領することを防ぐ方法あるいは手段に関する発明の特許適格性を否定された事案
本件において、第一審たる連邦地方裁判所は、「こうした商売を営むものであるならば、容易に思いつく方法である」として、特許適格性を否定した。控訴審では、この発明における物理的な手段である伝票と控えの用紙そのものには新規性はないとしたうえで、「ビジネスのシステムは、それを実行するための手段から切り放されている場合には技術とは解釈できない」として、本件クレームは法定の主題に当たらないものとした。
<Johnston事件>
事案:デジタルコンピューターによる経理帳簿自動記載システムに関する発明について、特許適格性が認められた事案
PTO審査部は、このクレームは「銀行業務の手法の独占を許すことになる」として、拒絶審査を行った。しかし、それを不服とする発明者(Johnston)は、CCPAに不服を申し立てた。CCPAは、「本件の装置クレームは、ビジネスの方法や、ましてや簿記の方法を目的としているわけではない」ため、「記帳のための機械システム」に関する本件クレームに特許適格性がないとはいえないとした。また、本件特許の範囲が、あくまでクレームに示された機械に留まり、「銀行業務の方法そのものに特許が付与されているわけではない」ことを強調した。
<Merrill Lynch事件>
事案:CMA(cash management account)に関する発明の特許適格性が認められ得るものとされたもの。
注)CMA...証券売買用の決済口座、MMF売買用の口座、クレジットカード決済用の
口座の3つをくみあわせたもの。
原告は、本件特許は「ビジネスの方法に過ぎない」と主張したが、コンピュータープログラムを使ったオペレーションシステムであり、これは特許法にいう技術の範疇に含まれるものとした。しかし、実際のところ、Johnston事件と同じように、ビジネスの方法自体に特許性が認められているわけではない。ただ、この事件のクレームは、具体的にコンピュータープログラムの動作を含めたコンピューターの作業内容が明示されているわけではない。
裁判例(金融システムに関する特許紛争:日本)
<オムロンバンクシステム>
事案:1992年にオムロンのバンクシステム(スウィング機能付き総合口座)についての特許が公告された。(特公平4-1381)
日本において、金融界で特許権に関する関心が高まったきっかけとなった。しかし、最終的には、「進歩性」がないとして本件特許申請に対して拒絶査定がなされた。
<注文授受兼生産自動化飲食店店舗装置>
<証券店舗の接客用業務設備>
これら2つは、「発明」の要件である「自然法則の利用」という条件の認定を多少あいまいにしている。が、オンライン化したカウンターとかV字型のカウンターといったかたちでビジネスの方法についてのアイディアが具現化されている事と思われる。
<まとめ>
新たに開発した金融商品やサービスに関する特許が出願されると、そのクレームが抽象的なアイディアに過ぎない場合には特許法の保護対象とはならないが、装置やシステム等による具体的な応用がなされていれば特許法の保護対象にはなりうる。特に、金融商品やサービスについてのアイディアを具体化する手段としてコンピューター・ハードウェアを用いる場合には、コンピューター・ソフトウェア関連発明の判断基準によって特許適格性が判断される。具体的に言うと、アメリカでは「数学的アルゴリズムが物理的要素に応用されているか」、日本では「ハードウェア資源が利用されているかどうか」が判断の重要なポイントとされる。
4.4 独占禁止法と、著作権
一般に、コンピューターを使用するに当たっては、application program(AP)と呼ばれるプログラムを用いて、その目的(作業)を果たすことになるのであるが、そのプログラム自体からの情報を文字表示したり、キーボードからの入力を依頼するプログラムが、operating system(OS)とよばれるものである。この時、APとOSの間の規約(protocol)が、API(application program interface)である。米国マイクロソフト社が、windows95を発売する際に、セットとしてマイクロソフトネットへ参加できるというソフトも付随した。それが、「ウィンテル包囲網による、通信ネットへのなぐりこみ」と解釈され、独禁法に違反するものではないかとして、公正取引委員会が動きだことがある。
注>ウィンテル:ウィンドウズをOSとし、インテル社のPentiumをCPUとしたパソコンが、世界中で圧倒的なシェアをほこっている。特に、世界No1.2のシェアを誇る、商用ネットCompuServe ,AOL(American online network)からの反発が激しかったのは想像に難くないであろう。マイクロソフトネットは、そのため、利用者数を制限することで、公正取引委員会からの捜査を免れた。
また、IBM社も、米国司法省によりシャーマン法2条に違反するものとして訴追をうけ一時は分割案もでていたことがあるが、このころプログラムというもの自体が著作権をもって保護されるという案はなかった。(唯一、アメリカで、トレードシークレットにとして保護されていたのみである。)しかし、実際このIBMに対する訴訟は82年1月にとりさげられた。と同時に、IBM社は、日本の企業(富士通・日立など)にたいして、知的所有権紛争を開始し、もって勝利した。(IBM産業スパイ事件)
5. 電子マネーの技法が特許権を獲得できるのか | ||
5.1 米国シティーバンクの特許
アメリカでのシティーバンクの特許は、1991年11月に出願され、現在この発明の特許はアメリカで認められている。この特許の特徴は大きくいうと3つある。
1つめは、このシステムの要素が「銀行または金融機関」「コルレス銀行」「複数の取り引き装置」「発行銀行及びコルレス銀行に関連する出納装置」「決済銀行」「データ通信ネットワーク」「安全保障機構」と、電子マネー関係に必要と思われる機関を全て網羅している事。
2つめは、多目的ペーパレス支払方式を提供し、それをもって取り引きが加入者間でオンライン・オフラインいずれにおいても実施される事。更に、通常の通貨と交換可能な電子マネーを用いた電子通貨システムで、多種通貨型の電子マネーを利用可能にしている事。
3つめは、電子マネーを発生するための金銭モジュール・出納モジュール・取引モジュールなど、電子通貨の流通において必要なプロセッサーの利用を全て想定している電子通貨システムであるという事。
特に、シティバンク特許は、銀行が必須の構成要件となっており、第1クレームを見る限り、転々流通されていく電子通貨について発行銀行が受け戻しの責任を負うために(初期の貨幣的価値を担保するために)必要な技術、特に取引モジュールで移転レコードを発生させて電子通貨とともに移転させていくことにより、経由した所有者を追跡して発行銀行にたどり着くことができるようになっている点が特徴といえ、また、ネットワークを前提とした特許なので、その構成要素である「通過の電子的象徴」,「金銭発生モジュール」,「出納モジュール」や「取引モジュール」が各国に分散している場合には1国内での発明の実施に該当しなくなるので、権利侵害を免れる方法もありうる。
まず思い付くのが、これは先述の「ビジネスの方法」にあたらないか、という事である。つまり、彼らの特許は、コンピューターのプログラムなどといったものではなく、あくまでも「方法」の提示をなしているものであり、これは明らかに「ビジネスの方法」にあたる、ということである。しかし、先述の通り、ビジネスの方法は、それ自体では特許性を有するものではないが、「数学的アルゴリズムが物理的要素に応用されているか」が満たされれば、歴然とした特許足り得る、ということ、また、産業界へのインパクトを考えると、少なくともアメリカでは特許性は認められて当然という事になる(この点は、アメリカでは、先述のカーマーカーの例にもあったように、日本では考えないような事を平気で特許を取る風潮がある)。特に、上のメリルリンチ事件にあるように、具体的にコンピュータープログラムの動作を含めたコンピューターの作業内容が明示されているわけではないので、逆に特許性が認められやすかったのではないかと考える。次に、アメリカの特許制度では、先述のように、「有効性」が推定されるのみであるので、NTT(以下に記述)がこれに対して抗議をなすことが少なくともアメリカでは可能であろうという事である。更に、「セカンダリーコンシダレーション(3)」でふれた、「自明性」の推定の項で、NTTとシティーバンクがなした特許出願がほぼ同時期である事を考えると(NTTのほうが少し早い??平成2年??)、アメリカの特許の要件を満たしていないようにも思えてくる。
発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」(特許法第2条1項)と定義されている。ここで「自然法則」とは、自然界において経験的に見い出される法則ををいい、人間が案出したルール等は含まれないとされおり、その意味で商品の陳列方法やビジネスの手法等は発明の対象から除外されてしまっている。しかし、一方、ソフトウエア関連発明については、簡単にいえば、ハードウエア資源を有効に利用していれば(審査基準)発明として成立する余地があり、例としてパソコン等の階層メニュー構造について、審査基準では、上位のメニューと下位のメニューとが記憶装置内のアドレス付けにより関連付けられていればハードウエア資源を有効に利用しているとした実例が挙げられる。明細書の記述テクニックにもよるが、このような形で特許を取得すれば階層メニュー構造にしたユーザーインターフェースそのものを権利化できる。 この考え方を適用すれば、単にハードウエア資源を利用しただけでは発明は成立しないが、もう一歩進んでハードウエア資源を有効に利用していれば発明として成立する。その結果その特許の権利の効力がビジネス方法に及ぶ場合もあるとされる。
5.2 日本におけるNTTの特許
5.2.1クリッパーチップにかわる新しい技術。
BLACK BOXをいれず(日本の憲法の「検閲の禁止」に触れないように)、アメリカのクリッパーチップのような国家検閲を可能とするシステムではなく、しかも優れた技術であるため、関心が高まっている。
5.2.2 電子商取引のシステムに関する特許(※注3)
デジキャッシュ社のシステムとは違い、インターネットを通じて、電子マネーが転々流通(例えば、「イシュアー」→「顧客」→「店」→→「店」のように、「店」から「店」への流通を可能とする電子決済システム)が可能となる。ところで、このNTTの特許と、米シティーバンクの特許に類似性はみいだせるのだろうか。もし見出せるとすると、米シティーバンクの出願している特許は明らかに「新規性」を満たさず、この請求は、日本特許法29条の「特許の要件」(特許出願前に日本国内において公然実施された発明ではないこと)を満たさず、原則として特許は認められないはずであろう。更に、もしNTTが他国でもこのシステムを特許として請願していれば、米シティーバンクのシステム自体、他の国でも新規性を持たないことになる。
#パリ条約:優先権制度(4条)
ただし、優先権制度は、特許の場合1年間(第一国での出願から第二国への出願に関して)である。とすると、もはやこの手をNTTがつかうことはできず、やはりあくまで日本国内に於いての米シティーバンクのシステムの新規性だけが奪われるのみになるのだろうか。また、アメリカの特許法の「均等論」を使う事で、この特許をアメリカで阻止する事ができるのだろうか。しかし、いったん特許を取られてしまった場合に、その後で無効を主張するのも、難しそうである。(CAFC設立後、特許侵害紛争における特許の無効判決が60%から30%へと減少した)
6. CONCLUSION | ||
米シティーバンクの出願している特許は、日本の金融機関、特に銀行にとって死活問題である。事実、都市銀行の大部分は、このシステムに対する抗議をだしている。ところが、日本の有数の優良企業たるNTTが電子マネー関係の特許をすでにとったという話があり、これをもとに、米シティーにたいする包囲網を形成しないことには、邦銀はシティーバンクの特許にたいして莫大な使用料をはらわざるを得なくなり、さらに、もしかすると邦銀のうちのどこかが専用使用権を獲得して、他銀行に対して利用権を請求するようになるかもしれない(一方、弁護士や弁理士の間では、このパテントライセンス料は少額になるのではないか、という議論がなされているそうである)。
その特許がもし既に取られているとするならば、今年1月施行の改正特許法の「事後異議申立て」制度がつかえそうであったが、これも附則により、拒まれる事となってしまった。また、「新規性」「有用性」という観点からも、若干の問題点を残していたシステム(あくまで個人的な意見)であったにも拘らず、認められる、というのは若干納得のいかないところではある。
この問題は工業所有権の属地主義の問題、法の域外適用、外国判決の承認の問題にもからんでくるとおもわれる。特に、後者に於いては、もし仮に日本でシティーバンクの特許請求が認められたとして、日本で特許侵害の判決が出た場合、アメリカにあるサーバーも差し止めできるかどうかの問題である(知的所有権問題では、「IBM対 日立」事件)。つまり、このシステム自体がグローバルなものであることにも関係し、例えばこのシステムが有効に利用されるためには、日本・アメリカ・欧州などといったところにそれぞれサーバをおいて、外国為替を行うものだから、例えば、日本やアメリカにサーバーをおいたとして、もし日本で侵害判決がなされると、アメリカのサーバも利用停止にする事ができるのか、という問題である。この点を含めて、今後大いに議論がなされそうである。さらに、アメリカが1994年8月に日米包括経済協議の中の知的所有権交渉のなかで日本側に要求した「特許後の異議申立て」制度(今年1月の特許法改正のメルクマール)を使う事で、もしかするとシティーバンクがすでにとったと(弁理士の酒井先生がおっしゃっていたが)されている特許に対して日本側として反論できたのではないか、という事も考えたが、これについては上記の(1)により、破棄せざるをえない。しかし、アメリカで取られた特許については、アメリカの「均等論」を使う事によって阻止できるのではないか、と考える。(余談であるが、日本の特許法においても、「均等論」を導入すべきとの見解も多い。この点につき、認知限度論などの否定的な見解もあるが、特許法70条の解釈の問題や、WIPO特許調和条約との関係から、今後も大いにいに議論がなされる事であろう)
電子商取引を含めたネットワークでの知的所有権問題は、まだまだ沢山存在する。ここには詳しく挙げなかったが、例えばネットワーク間でのソフトウェアの流通に絡めた、著作権の問題(ある一定の取り決めにしたがってデータ変換されたソフトの頒布など)、また、Internet Domain名と商標との関係(電子商取引における市場参入の位相で考えられる)、バーチャルモール(NTTデータ通信の商標名)内での、商標記載や、WWWにおける画像等の著作権(WWWの画像データを取り込む事が、著作権法で言う「複製」にあたるか否か)、更に、コンピューター関係で言うと、ソフトウェアの特許性なども、大いに議論されるであろう。私たちの班は、電子マネーが導入されたときのドメスティックな法律の問題点や、これからのあり方を模索する事を行って来たが、ネットワークを通した電子商取引という事を考えると、さらに、Internet等のワールドワイドなネットを通じたものたりうることを考えると、知的所有権や、強いては独占禁止法(反トラスト法)に絡む問題ともなりうるのである。
7. 参考文献その他 | ||
<注>この文書を作成するにあたり、以下の書物を参考にさせていただいた。
「日米特許摩擦」 塩入明 著 [中央経済社] 1993
「特許の文明史」 守誠 著 [新潮選書] 1994
「逐条解説改正特許法」 熊谷健一 著 [有斐閣] 1995
「工業所有権法逐条解説第13版」 特許庁 著 [社団法人発明協会] 1996
「パリ条約コンメンタール改訂版」 [法学書院] 1995
「新版国際経済法」 丹宗暁信・山手治之・小原喜雄 編 [青林書院] 1993
「電子金融の衝撃--銀行が消える日-」 日本経済新聞社 編 [日本経済新聞社] 1996
「国際民事訴訟法」 石黒一憲 著 [新世社] 1996 (5章)
「電子商取引環境整備研究会中間報告」 通商産業省公報
「金融研究」 1995 / 7
「特許公報 特平7-111723」(シティーバンク:電子通貨システムに関する特許出願公告)
※注1
この時感じた「違和感」というのが、恐らく、「ビジネスの手法」に対する違和感、であったのだろうと思います・・。(2001/07/01)
※注2
日本に措いて、Intellectual Property の翻訳が「知的所有権」となっているあたり、やはり知的な活動に対する日米の差異が生じざるを得ないのだろうな、という気がしています。知的活動を積極的に活用し利益を生む、というのが米国の考え方であり、日本は「ただ持っているだけ」という考え方である気が・・・。(2001/02/14)
※注3
NTTは、「電子現金実現方法及び其の装置」という名称に措いて、特許を日本ならびにアメリカ、カナダ、フランス、ドイツで登録している。(特公平2-88838)
その後、多数の電子現金方法に関する特許や日銀と共同の特許などを出願、登録したが、これは、(携帯電話,
PHSの有効利用法を当時から考えていた筆者にとっては)NTTあるいはその子会社が何らかの形で銀行業務をやることがありうるだろう、ということを予感させるものであった。事実、携帯電話におけるマイクロペイメントは、きわめて日本に措いて定着しうるものであり、現に、行われている事実もある。(2001/07/01)
#実は、丁度、インターネット時代における「決済の手法」(MONDEX型、ecash型、等等)についても、同ゼミにおいて議論されてたんですよ。其のときに、ふと思ったことではあったんですが・・・。(日本は、おかみからくる請求書には疑問をもたないで自動引き落としを受ける傾向にあるし)
追伸: (2000/08/16)
まさか、3・4年前に書いた、これが、今話題の「ビジネスモデル特許」に関係しているとは・・・。(ちなみに、ビジネスモデルという英語はなく、Business Method Patent、つまり、<<ビジネスの方法>>に対する特許、というのが、ビジネスモデル特許を指します。)
ビジネスモデル特許は、平成10年7月、米国において「「ビジネス方法」に該当するからといって直ちに特許性が否定される訳ではない」などとした判決(ステート・ストリート・バンク事件)が出されたことを契機として、一定の条件の元認められるようになった経緯があります。この文書を書いたのが平成8年ですから、その2年後ですね。
Citibank EMS
に関し、当時に比して、この話題に関する本が充実しています。例えば、「電子マネーと特許法」(弘文堂)
相澤英孝編著
などが非常にまとめられています。当時、私はシステム全体のことや特許法そのものについてもあまり知識がありませんでしたから、今読み直してみると、結構勘違いしているな、と思える部分も多いです。(例えば、当時、「レコード」という言葉に、CDの前の音楽レコードなどをイメージしましたから。勿論、データベースのテーブルにおける<行>のことですけどね)
ビジネスモデル特許については、書きたいことがいっぱいありますが、少なくとも、あまり過度に敏感になる必要はあるまい、ということです。今は、プロパテント時代・・つまり、特許権が優勢な時代です。しかし、またいつしか、アンチパテント時代が必ずやってきます(ビジネスモデル特許の乱立で、ベンチャー企業の芽がどんどんつぶされるようになることは、想像に難くなく、このような現象になることを米国は「その特性上」許さないのです。再度、米国・日本の特許法の存在理由について考えてみましょう。)。その間をしのぐために、郵便局の「確定日付郵便」をうまく利用し、自分自身に郵便物を送ることで(ファイリングはしっかりしてください)、対抗要件を備えてください。。。。。。。
おまけのおまけ※次の年のゼミ(商法:江頭先生):
連結会計制度について